シングルマザーの貧困が問題になっているのは知っていますか?
離婚を考えている人にとっては、とても心配な問題ですよね。
原因としては、養育費が少なかったり、そもそも支払いを受けていなかったり、子供を抱えながらの就職が難しかったり、様々な問題点があげられます。
その中のひとつ、養育費の相場がそもそも低すぎる問題について、日弁連が見直しを図り新たな算定表を打ち出しました。
これはとてもありがたい動きです( ;∀;)
そして気になるのが「いつから採用されて、いくらくらいの増額が見込まれるのか?」…について調べてみました。
この記事の目次
そもそも養育費とは
1.養育費とは

養育費とは、未成熟である子供が、親から自立し社会に出るまでに必要とされる費用のことです。
具体的には、衣食住に関する費用や、教育・医療などにかかる費用、適度な娯楽費用など、子供の生活にかかる費用全般のことを指します。
最近では大学への進学率が高まり、それに伴い塾に通う子供も増えていることから、教育費が大きな割合を占めるようになっています。
2.養育費の相場とは?
養育費の金額は、夫婦の話し合いにより自由に決めることができます。
方法としては、「これまでの子育て状況から必要な金額を算出して、夫婦それぞれの分担割合を決めて、養育費額を決定する」というのが最も現実的だと思います。
とはいえ、離婚する夫婦にとっては、たとえ子供のためとはいえ前向きな話し合いは難しく、なかなか折り合いがつかないものです。
そうなると、やはり何か基準とできるものが欲しく、こうした際に相場として使用されるのが「養育費算定表」です。
養育費算定表は、東京・大阪の裁判官が平成15年に作成したもので、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判などで養育費を算定する際の参考資料として使われています。
「養育費算定表」はこちら。
3.養育費算定表の使い方
手順1.養育費算定表を選択する
養育費算定表の中から、使用する表を選択します。
右上に「養育費」と書いてあるシートの中から、「子供の人数や年齢」で該当するものを選びます。
※この算定表が使用できるのは、子供をどちらか一方の親が引き取る場合です。
「婚姻費用」とは?
別居や家庭内別居、DVなどで生活費をくれない夫に生活費の請求をする場合の相場表として使用されるものです。
手順2.夫婦の年収を表に当てはめる
選択した算定表にて、義務者と権利者のそれぞれの年収箇所をマークします。
縦軸が「義務者の年収」、横軸が「権利者の年収」で、「義務者」は養育費を支払う義務のある側、「権利者」は養育費をもらう権利のある側となります。
縦軸と横軸の年収にそれぞれマークできたら、義務者(縦軸)はそこから右へ線を引き、権利者(横軸)は上に向かって線を引き、交差したところに記載してある金額が養育費の算定額となります。
なお、収入は「給与」と「自営」の二種類に分けられているため、給与収入の場合は「給与」の軸を使い、自営業の場合は「自営」の軸を使用してください。
給与収入の場合、手取り金額ではなく、税引き前の「総収入金額」を見ます。源泉徴収票でいえば「支払金額」です。
自営業の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加算した額となります。
期待の養育費新算定表とは?
1.変更の経緯と概要
現在使われている「養育費算定表」については、「金額が低すぎる」という批判が多くあります。
現に、母子家庭の貧困は深刻な問題になっているし、それに伴い子供に十分な教育を受けさせることができていない家庭が増えています。
そこで、日本弁護士連合会(日弁連)は、新たな算定方式と算定表を打ち出し、これを利用すれば養育費がこれまでの1.5倍に上がるものとなります。
そもそも、民法では、養育費を支払う親は子供に対して親と同レベルの生活水準を保障する「生活保持義務」を負っていますが、現行の算定表では金額が低く見合っていない状態なのです。
更には、養育費算定表が作成された2003年以降、景気変動や税制改正などの世の中の動きが大きくあったにもかかわらず、見直しや改正がなされずじまい…。
このような中で、日弁連の新算定表は、ひとり親世帯、特に母子家庭においてはとても期待されるものとなります。
2.日弁連が提言した養育費新算定表はこれ!
早速チェック!
2017年7月には本も発売されてます。
↓ ↓ ↓ ↓
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/164b1746.6dd6565f.164b1747.851e819b/?me_id=1213310&item_id=18648790&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4064%2F9784817844064.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4064%2F9784817844064.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル 具体事例と活用方法 [ 日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会 ] |
3.養育費金額はどのくらい変わるの?
たとえば、下記の場合を見てみましょう。
・子供1人 15歳
・子供と同居している母親の年収200万円
・養育費を支払う父親の年収500万円
現行の算定表では「5万円」だったのが、新算定表では「9万円」となる見込みです。
あとは夫婦の話し合いになりますが、5万円で話を始めるのと9万円で話を始めるのでは、着地点は大きく変わってくると思います。
そもそも、現行の金額はなんなんだ…と愕然としてしまうくらいの金額差ですよね(*_*;
養育費の実際はどうなの…?ということでこちらもどうぞ。
4.養育費新算定表はいつから採用されるの?
新算定表が打ち出されたものの、いつから採用されるのかという期日は明確にはありません。
なぜなら、そもそも現行で使われている「養育費算定表」も強制力があるわけではないからです。
裁判官が作って、裁判所で基準として利用されているものの、強制されるものではないというのは驚きというか、残念ですよね。
もちろん、裁判で養育費の支払いが確定した場合はその支払いは強制力を持ちますが、金額は必ずしも算定表のとおりではないということです。
さらに、『来月から「新算定表」を使いますよ』などという一斉切り替えや新算定表使用の強制というのもありません。
今後の動きとしては、弁護士が率先して「新算定表」を使っていくことで現場に定着させていくこと。
それにより、裁判所や世間も新方式の方が良いと認め、浸透していくということだそうです。
養育費の不払いが多い中で、少しくらい強制力を持たせてほしいところではありますが、まずは「新算定表」ができたことに期待を寄せたいと思います。
離婚後の養育費についてはこちら。
まとめ
新算定表が発表されたからといって、即日切り替わるわけではありませんが、これはシングルマザーにとってとても大きな希望の星となると思います。
これから夫と話し合いをする予定の方はぜひ、新算定表を目の前に突きつけてやりましょう!
弁護士に相談中の方や相談予定がある方、調停をする予定の方は、弁護士や裁判所の方から話をしてもらえると良いのですが、もし現行の算定表を使用されている場合は新算定表の使用を訴えてみましょう。
養育費の支払い額や不払いに悩んでいる人が多い分、一人一人が実際に使用していくことで、現状をひっくり返せるほどの大きな力となると思います!
自分や子供の生活がかかっているのですから、遠慮や泣き寝入りをしている場合ではないですよね。
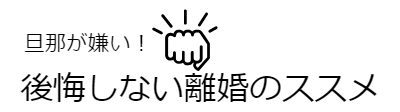






















コメントを残す