「養育費はいくらもらえるんだろう?」
離婚を考えた時に疑問に思う人は多いと思います。
なかには、「払ってもらえないかも…」「自己都合の離婚だから請求できないわ…」と諦め気味の人もいるかもしれませんが、それは間違いです!
養育費の受け取りは子供が持つ権利で、親には支払い義務があります。
養育費について知り、「子供のために1円でも多く請求する!」という意気込みで話し合いに臨んで欲しいと思います。
そもそも養育費とは?

「夫は借金があるから請求しても払ってもらえない」「私の不倫が原因だから請求できないでしょう…」
なんて思っている方、そんなことはありません!
まず「養育費とは何か?」を知ることからはじめましょう。
1.養育費は子供の生活費
養育費とは、「子供が自立するまでに必要な生活費」で、衣食住に必要な費用や、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
原則的には「子供が未成熟の間」支払われるものとされています。
2.子供には受け取る権利、親には支払い義務
養育費の支払いを受ける権利は、子供が持つ権利です。
親には支払い義務が課せられています。
そのため、父母の離婚理由がなんであれ関係ありませんし、父母が「支払わない、受け取らない」と勝手に決めるものでもありません。
3.「払わない」「もらわない」は許される?
「とにかく離婚したいから養育費の請求なんてしなかった」という話を聞いたことはありませんか?
この気持ち、私もとても分かります。
でも養育費は子供のためのもの。これって許されるのでしょうか?
他にも、こんなケースがあります。
・自分の不倫が原因で離婚することになったため、夫に養育費を請求できない…
・養育費はいらないから二度と子供に会わないで!
・子供に会わせてくれないなら養育費は払わない!
・夫は借金があるから養育費を請求してもどうせ払ってもらえない…
・慰謝料や財産分与をもらったので、養育費までもらえない…
うーん、どうなんでしょう…。
詳しくは、下記で!
養育費のあるある問題。こんな時どうなるんだろう…?”(-“”-)”
養育費について決めておくべきは3つ
養育費の支払いについては、最低限、次の3つの項目について決めておきましょう。
1.養育費の額(子供一人につき月額いくら、という形で)
2.養育費の支払い期間(いつから、いつまで)
3.養育費の支払い時期と振込先(毎月○日に、○○口座まで)
最終的には、支払いが止まってしまった時に強制執行をかけられるよう、協議内容を公正証書にしておくことをおすすめします。
養育費の金額の決め方は?
1.自由に決めることができる
養育費の額は「夫婦の話し合い」で自由に決めることができます。
その際、基準となるのは、「離婚後も、父母(主に養育費を支払う側)と同じ生活水準を保てるようにする」ということです(生活保持義務)。
つまり、離婚後の父親は独身に戻って豪遊しているのに対し、母親と子供はギリギリの生活…なんていうことは許されず、親と子が同水準の生活を送れるように養育費の額を設定することが求められます。
そのため、それぞれの年収や離婚前の生活内容等を踏まえて考えるのが良いでしょう。
とはいえ、離婚する夫婦にとっては、いくら子供のためとはいえお金に関する話し合いは難しいものがありますよね…。
そこで参考となるのが、「養育費算定表」です。
2.相場=養育費算定表
「養育費算定表」は、子供の人数や年齢別に、夫婦それぞれの年収から養育費金額を算定できるように表形式で作成されている資料です。
家庭裁判所で行われる離婚調停や離婚裁判などで、養育費算定の参考資料として使われています。
見方は簡単ですので、夫婦で話し合う際に「相場」の参考資料として使用すると、話を進めやすいでしょう。
●養育費算定表のダウンロードはこちら
【朗報】新算定表発表で1.5倍に増額!
既存の養育費算定表は「金額が低すぎる」という声が多かったことから、日本弁護士連合会(日弁連)が2016年12月に新たな算定表を打ち出しました。
この「新算定表」では、養育費がこれまでの約1.5倍に増額された内容となっており、大きな期待が寄せられています。
養育費算定表の使い方
1.養育費算定表を用意する
まずは、養育費算定表をダウンロードして、可能であれば印刷をしましょう。
算定表は2種類あります。
新算定表は、これまでの算定表より増額された内容となっていますが、昨年12月に発表されたばかりなので浸透度はまだ低い状況です。
一人一人が使用していくことで浸透度を高めていきましょう( `ー´)ノ
2.算定表の中から使用する表を選ぶ
右上に「養育費」と書いてあるシートの中から、「子供の人数や年齢」で該当するものを選びます。
※「算定表」と「新算定表」では、子供の年齢の分け方が異なるため注意してください。
※使用できるのは、子供をどちらか一方の親が引き取る場合のみです。
ちなみに、「婚姻費用」と書いてある表は何かご存知ですか?
これは、別居や家庭内別居、DVなどで夫が生活費を渡してくれない状況にあり、夫に生活費を請求する場合の相場表として使用されるものです。
夫が生活費をくれない!と悩んでいる方はこちらも。
3.夫婦の年収を表に当てはめる
縦軸と横軸に夫婦それぞれの年収を当てはめます。
・縦軸=義務者の年収=養育費を支払う義務がある側
・横軸=権利者の年収=養育費を受け取る権利のある側
縦軸は年収から右に矢印をのばし、横軸は年収から上に矢印をのばし、交差したところにある金額が養育費の算定額です。
養育費の支払い期間は?
1.いつからいつまでもらえる?
「請求した日」から、原則的には「子供が未成熟の間」支払うものとされています。
未成熟とは、自立して経済生活を送れる状態になっていないことをいい、必ずしも成人までとは限りません。
たとえ成人していても、病気や障害などにより扶養が必要な場合は未成熟子の扱いとなるし、逆に18歳で就職している場合は自立しているとみなされる場合があります。
2.大学を卒業するまでもらえる?
大学生は、まだ経済的な自立ができず親の扶養に入っている子供が多いため、養育費の支払いを受けることができると考えられます。
とはいえ、子供が幼くて大学進学までに年数がある場合は、大学進学の意思があるのかも分かりませんよね。
こんな時、どういう風に決めておくのが良いと思いますか?
・とりあえず「子供が20歳になるまで」としておき、大学進学時に協議する
・高校卒業後に就職するかもしれないから「18歳まで」としておき、大学進学時に協議する
・「大学進学時には大学を卒業するまで」としておく
決め方ひとつで後々問題になることも…。
詳しくは下記でご確認を!
大学進学時の養育費請求の詳細はこちらで確認!
幼稚園から大学までの学費はいくら必要?
入学金などは月々の養育費とは別に請求することが可能です(/・ω・)/
3.再婚したらもらえなくなる?
養育費をもらっていた側が再婚する場合、支払っていた側が再婚する場合とありますが、再婚したら養育費の支払いはどうなるのでしょうか?
そもそも養育費とは、子供の生活費のために払われるものであり、親に課せられた義務です。
そのため、親が再婚したからといって、子供にとって親であることに変わりはないため、払わなくてよくなるものではありません。
ただ、事情によっては、減額が認められることがあります。
「私は再婚するつもりないから関係ない」と思っていたら…元夫が早々に再婚なんてことも。
「子供が産まれるから減額してくれ」と言われたらどうしますか?
詳しくは下記でご確認を!
自分が再婚、相手が再婚した場合の養育費について、詳細はこちら!
養育費の不払い問題
1.養育費の支払い率は2割
厚生労働省の「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」から、母子世帯における養育費の受け取り状況を調べてみたところ、下記のような結果でした。
【元夫から母親への支払い状況】
・現在も養育費を受けている 19.7%
・養育費を受けたことがある 15.8%
・養育費を受けたことがない 60.7%
10人中2人しか支払ってもらえていない…。
ちなみに、養育費の取り決めをして離婚した場合の支払い率は約50%でした。
取り決めをしていないよりはマシですが、低すぎです。
これは他人事ではありません!(;゚Д゚)
2.強制執行の問題点
「でも、払ってもらえない時は強制執行で給料差し押さえができるでしょ?」
と思ったかもしれません。
確かに、強制執行制度では、「養育費を支払わない相手方の財産を裁判所が差し押さえることができる」と定められています。
ただ、これには、相手方の現住所や財産の所在(預金口座)の特定が必要となっており、これが厄介なんです…。
だって、養育費の支払いから逃げるような相手なので、住所や預貯金口座を変更している可能性が高いし、本人に聞いたとしても教えてくれるはずありませんから。
つまり、現実的にはなかなか厳しいものなんです。
3.法務省の新制度に期待!
養育費の不払い問題を解消すべく、2016年11月から法務省で議論が始められています。
「裁判所を通じて相手方の預貯金口座を特定できるようにする」という法改正で、これが通れば、相手方の預金口座が分からなくても強制執行をかけることができるようになります。
とはいえ、新制度の開始は早くて2018年内…。
「不払い」や「逃げ得」が横行している中、今、自分でできる対策をとっておくことも必要です。
詳しくは下記記事にて。
許せない!養育費の不払い問題についてはこちら。
自分の夫だけならず、世の男性に対する信頼度が下がってしまいます…(-_-;)
養育費の受け取りを確実にするには
1.公正証書を作成する
養育費や慰謝料などの金銭の支払いについて取り決めができたら、その内容を「公正証書」にしておきましょう。
公正証書にするには、労力やお金がかかりますが、いざという時の効力や手間に大きな差が出てきます。
この時注意したいのが、「強制執行認諾約款」の文言を入れておくことです。
これは「支払い義務者(債務者)が支払いを怠った場合には、ただちに強制執行を受けることを了承している」ということを示すもので、相手方の支払いが滞った際に、裁判をすることなく強制執行をすることができます。
2.調停の場合は調停調書
調停を利用して養育費の取り決めをした場合には、調停成立時に「調停調書」という書面が作成されます。
公正証書と同じような効力を持つため、公正証書の作成は必要ありません。
もし、相手方が養育費を支払わない場合には、裁判所が相手方に対して督促(履行勧告)をし、それでも応じないようであれば財産を差押えて強制的に養育費を回収することができます。
3.夫の預金口座を押さえておく
離婚する前に、夫の預金口座を把握しておきましょう。
強制執行をかけるためには、相手の財産が入っている銀行名と支店名が必要になりますが、離婚してからこの情報を入手するのはとても難しいものです。
離婚後に預金口座を変更されてしまう可能性もありますが、できる限りの手は打っておくにこしたことはありません。
4.それでも養育費をもらえなくなってしまった場合は?
離婚前にどんなに手を打っていたとしても、養育費を払ってもらえなくなり、トンズラされてしまうことは起こり得ます…。
とても不安になるし、すごく腹立たしいことですよね。
けれど、話をしに行っても掛け合ってもらえなさそうだし…なんて泣き寝入りしてしまっている人も多いのではないでしょうか。
最悪、話し合いたくても所在が分からなくなってしまった…なんていう人も。
そんな時におすすめの方法を見つけましたので、お困りの場合はこちらもどうぞ。
まとめ
いかがでしたか?
養育費の支払いは、長く続くものなので、月額1万円の違いも15年続くと180万円変わってきます。
相手に言われるがままに決めていると、損をさせられるかもしれません。
自分や子供を守るために、知識を得て、対等に(できれば有利に)交渉できるようにしましょう!
離婚してこれから自活するとなると、何でも自分で考えて、自分で行動しなければいけなくなります。
離婚準備をしっかりすることは、そうした訓練となり、自信にもつながり、先々の後悔も防ぐことができます(*’ω’*)
※「養育費」に関する記事はこちらにまとめています。
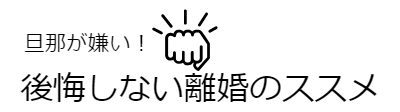














妻と別居中です。
養育費を請求されたので、私名義の通帳を渡し常識の範囲内で引き出して良いと言いました。因みに私の給料は人並みです(私30歳、妻26歳、娘2歳)。
最初は月約8万程度引き出され、私自身の生活が困難になりました。酷い時は給料前の銀行口座が140円になりました。私は4〜5万円にしてほしいと妻に言い、妻も了承しました。しかし、今月も妻は6万円引き出してます。
妻は別居を始めて夜の仕事をしてます(多分キャバクラかな?)。それ以外にも仕事をしているようですが、聞いても答えてくれません。給料も答えくれません。
私は住んでいる家の家賃等を払い、毎月節約しながら生活してますが、妻は実家なので私よりも手元に残るお金は多いと思います。勝手に別居を始められ、子供も連れ去られて一人で生活を強いられてます。離婚か修復かの話もしてくれないし、夫婦に関する事は何かと女性有利になって納得できないです。別居は申し出た方、子供を連れ出した方が有利ですか?妻の実家の両親は現役世代です。
カテゴリと違う内容になってすみません。
さんたくさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
現在別居中で、養育費として月6万~8万円くらい渡している(引き出されている)とのことですね。
貯金通帳を渡すとは…、さんたくさんは家族思いで優しい人ですね。
でも、何となくですが、奥さんの行動からすると、
修復というよりは、離婚に備えてお金を貯めておこうとしているように感じてしまいます(-_-;)
ちなみに、別居中であっても離婚前であれば、
養育費だけでなく奥さんの生活費も負担する義務があります(婚姻費用と言います)。
離婚したのであれば、奥さんを扶養する義務はなくなるので、子供の養育費だけ支払えば良くなります。
そうした上で、いくら渡すのが正解なのか…ですが、
これは夫婦の収入バランスによります。
家庭裁判所の「養育費算定表」の後ろの方にある「婚費算定表」を参考にしてみると良いですよ。
私が別居していた時は、夫年収500万くらいで、私が育休中で無収入でしたので、
婚姻費用として10万円もらっていました。
ただ、さんたくさんの場合、奥さんの収入が分からないので難しいところですよね…。
現在の金額に納得できない場合は、家庭裁判所で調停をするのはどうですか?
「婚姻費用分担調停」で、お互いの収入を明らかにして適正な金額を決めることができます。
それから、関係修復を望むのであれば「夫婦関係調整調停」、
離婚話を進めたいのであれば「離婚調停」も婚費分担調停と同時にすることができますよ。
最後にですが…
夫婦に関することは女性が有利…というわけではないかなぁと思います(;´Д`)
親権については、たしかに子供が幼い場合は母親が有利なことが多いですが、
離婚後の生活を考えると「有利」とか「得」とかいったことはありません。
小さな子供を抱えながら仕事をしていくのは大変です。
仕事と家庭の両立はもちろんのこと、まずは仕事に就くことがかなり大変です。
就職試験を受けても「すぐに休まれるから使えない」と思われてなかなか採用されないし、
採用してもらったとしても「どうせすぐに休むんでしょ」と思われて基本給を低く設定されたり…。
たとえ夜の仕事で稼いだとしても、年齢的に長く続けられるものではないし、簡単な仕事でもありません。
子供が小学生になったら、保育園に比べて帰宅時間が早くなるため、
17時半までの正社員勤務も難しくなるなど、より一層働きにくくなります。
実家暮らしだからお金がかからないかもしれませんが、
それはつまり親に金銭的負担をかけてしまっているということですよね。
それに、親世代は近所の目や親せき関係の目など世間体を気にする人が多いので、
小言を言われることもあるし、かなり肩身が狭い思いをします。
私がそうなんですが、苦労するのは分かっていても、
子供と2人で独立して生活したい…と日々願ってしまいます。
でも、独身時代のようにバリバリ残業して給料を得ることができないから、
それも簡単には叶わない…という。
だったら子供を手放せば?と思われるかもしれませんが、
それはできません(;´・ω・)
「子供がいるから大変」という話であって、子供が嫌いとかイヤとかいう話ではないので。
大変さは父親側が子供を引き取っても同じですしね。
今までのように「仕事でクタクタなんだから、勘弁してよ」なんて言ってられないです。
子供の食事や着替え、お風呂、歯磨き、洗濯、寝かしつけ、ゴミ出し…
などなど毎日やることはたくさんあります。
他にも肌着や服などの購入や散髪なども必要ですし、休みの日は遊び相手です。
女の方が大変!と言いたいわけではありませんが、
離婚後の妻の生活をちょっと想像してもらえると嬉しいです(;´∀`)
ということで、結婚して子供を授かったからには、
できることなら離婚しないで家族を続けていけるのがお互いにとって一番良いことだと思います。
勝手に別居をはじめられた…とのことですが、やはり何か理由があってのことですので、
その原因を解消して修復の道を進んでいかれることを願っています。
以上、長文失礼しました‼