養育費は「月額いくら」という形で取り決めますが、これとは別に「子供の入学や入院などで特別な費用がかかる場合は別途請求できる」ということを知っていますか?
子供を育てるにはお金がかかるため、もらえるものはもらっておきたいもの。
とはいえ、子供が一人目だと今後どのくらいお金がかかるのか未知の世界ではないですか?
そこで、今回は子供を育てる際に必要な教育費について調べてみました。
この記事の目次
養育費で入学金も請求できる?方法は?
1.公正証書の記載事項にもあります
公正証書に記載しておくべき内容の一つに、下記のような文言があります。
甲は、丙の進学・事故・傷病等、特段の事由により発生する費用が過大になり、通常の養育費の額を大幅に上回る場合、乙の申し出により、甲乙協議の上、別途その必要費用の全部又は一部を負担する。
つまり、(毎月の養育費は〇円としますが)
子供の進学や事故、病気療養などで、養育費では足りない時には別途費用を負担してもらいます…ということです。
月額の支払い額を決めることができたら安心してしまいますが、これから子供を育てていく中では大きなお金が必要になることが出てきます。
そうした際は、別居している父親にも費用分担の請求をすることができるのですが、いざその時に話を持ち掛けても知らぬ存ぜぬで逃げられてしまう可能性が…。
そのため、公正証書に記載しておくことがおすすめです。
2.金額まで決めておく?
先ほどの文言例では、
「その時が来たら話し合いで決める」となっていますが、
入学金等については「現時点で金額や支払時期を定めておく」という方法もあります。
その時が来てから決めるメリットとしては、
話し合いを持つ頃(数年後)には夫の年収も上がっていると想定されるため、現段階で金額を決めるより多くもらえる見込みがあるということです。
デメリットとしては、
離婚後に話し合いの場を持たなければいけないこと、万が一転職や失業されていた場合に請求できる見込みが少なくなることです。
今決めておくことのメリットやデメリットはこの逆ですね。
どちらが良いかは、夫の性格や夫婦の関係性次第…というところでしょう。
ちなみに、私の夫の場合は、「今決めておいた方が良さそう」派です。
理由としては…
・お金の話をすると毎回「金の亡者」となじられて喧嘩になるので嫌な話は離婚前に済ませておきたい
・先読み&貯金ができない人なので、後で請求すると「急に言われてもムリ」と断られそう
・将来年収は上がると思うけど、クビや転職の不安が大きい
ということで、公正証書に支払い時期や金額まで盛り込んでおきたいと思っています(-_-;)
「知らないと損する」養育費についての総集編
⇒ 養育費はいつまで?離婚前に押さえておくべき相場や計算方法と注意点
離婚前の準備は大切です(; ・`д・´)
すでに離婚してしまった場合の対処法はこちら
3.なかには拒否する夫も
夫によっては、金額も分からない約束をさせられることに抵抗を覚える人もいます。
私の夫もそうでした。
「俺はこんな事をわざわざ書かなくても子供のためには何だってする。公正証書に書かれるとやらされ感が出るため書きたくない。俺のことが信じられないのか」と。
「月〇万円も払ってやるのにまだ請求するつもり?欲深い人間だね」とも。
そんな言葉を信じられるなら離婚騒動に至ってないし、「ことが発生した場合は」という仮定的な話だし、そもそも子供のためなのに…(-_-;)
ちなみに、どんなに優しくて、いいパパだったとしても信じてはいけないです。
長い人生、これから何があるか分かりません。
再婚して新たに子供をもうけた途端、縁を切ろうとしてくる人もいますので、公正証書にはきちんと書いておくように説得しましょう。
4.夫の説得方法は?
夫が何に対して納得していないのかを聞いてみましょう。
それが分かれば、その問題点をひとつひとつ解消していけばいいのです。
夫の言いそうなこととしては、「そこまで自分が負担する義務があるのか?」「今決める必要があるのか?」「公正証書には書かなくてもいいのでは?」などでしょう。
対処法としては…
・「子供のため」に話し合っていることを改めて落ち着いて伝えてみる
・特別の費用が発生した際は分担請求できるもので、公正証書のひな型にも含まれている
・病気療養や大学費用などは仮定の話で合って、必ず請求するものではない
・全額払ってというわけではなく、分担のお願いをしている
・離婚後まで揉めないために、今決めておきたい
これらのことを説明し、それでも納得してもらえなければ、調停での話し合いを持ち掛けましょう。
「専門の人から説明してもらえれば、お互い納得できるでしょう」…と(´-ω-`)
5.子供にどうさせてあげたい?

母子家庭になるからといって、子供に十分な教育の機会を与えられないのは、親として責任を感じてしまうところではないでしょうか。
大学に行くかどうかは子供本人が決めることですが、現実として、大学進学は当たり前のように増えているし、大学を卒業しなければ面接すら受けることができない職業もあります。
そうした将来の夢や人生の選択肢を親の都合で狭めさせたくないものですよね。
もちろん、大学に行くことだけが「成功の道」というわけではなく、自分で自分の生きる道を見つけてもらうために、できるだけ広い選択肢を用意してあげられるようにしたいのです。
それは旦那さんも同じ気持ちだと思いますので、「子供にどうさせてあげたいか」を話し合ってみると良いかもしれません。
「塾にも行かせてあげたいよね」「英会話も習わせたいよね」「スポーツも何かさせたいね」「留学もいいね」
夫からこんな言葉を引き出せたらチャンスです。
「塾は月1万円くらいかなぁ?でも私のこれからの給料だと厳しいから、養育費もう少し協力してもらうことできるかな?」
なんていう交渉も可能かもしれません(=゚ω゚)ノ
子供の教育費の相場は?
1.幼稚園~高校までの教育費
子供の教育費にはいくらくらいかかるものなのでしょうか?
文部科学省が行っている「子どもの学習費調査」によると、幼稚園~高校までの間でかかる「学習費総額」は下記のとおりとなっています。
※学習費総額とは、学校教育費(入学金、授業料、制服、教科書など)、学校給食費、学校外活動費(塾や習い事など)を合算したものです。
●幼稚園(3年間)
| 公立 | 634,881円 |
| 私立 | 1,492,823円 |
●小学校(6年間)
| 公立 | 1,924,383円 |
| 私立 | 9,215,345円 |
●中学校(3年間)
| 公立 | 1,444,824円 |
| 私立 | 4,017,303円 |
●高校(3年間)
| 公立 | 1,226,823円 |
| 私立 | 2,973,792円 |
【幼稚園~高校までのデータ】
2.大学の教育費
日本政策金融公庫が「国の教育ローン」を利用した人を対象に行っている「教育費負担の実態調査」によると、大学在学時にかかる費用は下記のとおりとなっています。
| 入学費用 | 在学費用 | 合計 | |
| 短大 | 70.5万円 | 132.9万円 | 203.4万円 |
| 国公立大学 | 81.9万円 | 375.6万円 | 457.5万円 |
| 私立大学(文系) | 106.7万円 | 568.8万円 | 675.5万円 |
| 私立大学(理系) | 106.0万円 | 712.0万円 | 818.0万円 |
※入学費用=受験費用+入学金+入学しなかった学校への納付金
※在学費用=学校教育費(授業料、通学費、教科書代など)+家庭教育費(塾、参考書、習い事など)
【大学に関するデータ】
一人で負担するには大きすぎますよね(゚Д゚;)
3.つまり教育費は…
あとは、公立か私立か、希望に合わせて足し算していけば、教育費用の合計を知ることができます。
大きな数字が並んでめまいがしてきそうですね…。
幼稚園から大学まですべて国公立で進んだとしても、約1,000万円かかるということになります。
高校だけ私立だった場合で、1,156万円です。
子供が複数人いるとなると…あわわわわ(*_*;
この金額は教育関係のお金だけなので、実際の生活には食費や被服費、日用品代、お小遣い、ケータイ代、散髪代…挙げきれないほどの費用がかかります。
こういった現実的な費用も提示したうえで話をするようにすると、旦那さんも納得してくれるのではないでしょうか。
離婚後の母子家庭の生活は?
⇒ 離婚後の母子手当はいくらもらえる?養育費と児童扶養手当で生活できる?
教育費を計画的に効率よく貯めるなら学資保険がおすすめ!(外部サイトです)
⇒ 一番お金が貯まる学資保険がすぐ分かる!
まとめ
離婚により夫婦の縁は切れますが、それぞれが子供の親であることに変わりはありません。
「二度と顔を合わせたくない」という人も多いとは思いますが、一人で抱え込める金額ではありません。
離婚後も、子供の親として協力し合うべきところは互いに協力していかなければならない、それが子供をもった親の責任なのだと思います。
と、自分に言い聞かせている私です(-_-;)
顔を合わせるのは嫌ですが、旦那が協力してくれるというのは恵まれていることなんですよね…。
※「養育費」に関する記事はこちらにまとめています。
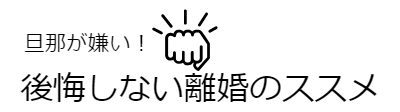














コメントを残す