「親権は絶対に譲らない!」
離婚する際、旦那さんに言い張られたらどうしますか?
いわゆる、親権争い。
「子供が小さいうちは母親の方が有利」というのもよく聞きますが、本当なんでしょうか?
親権を確実に得るために、まずは裁判所が親権者に求める条件を確認しておきましょう。
この記事の目次
本当に母親の方が有利なの?
1.母親の親権獲得率はどのくらい?
母親の親権獲得割合は、約8~9割ほど。
子供が低年齢であるほど、母親が有利と言われています。
2.母親が有利な理由は?
大きく2つあります。
1つ目が、「母親優先の原則」
これは、低年齢の子(特に乳幼児)については、母親の存在が不可欠であるとして、母親を親権者に指定するべきという考えです。
子供が幼いうちは、きめ細やかな育児や家事をする必要があることが理由です。
2つ目は、「監護の継続性」
子供にとっては、親と子の精神的な結びつきが重要であり、この結びつきを断絶させるような監護者の変更はするべきではないという考え方です。
たとえば、夫婦が別居した後、幼い子が片方の親に引き取られ、親子間に絆と愛着が形成されている場合は、そのままの状態を維持するべきということ。
つまり、別居時に子供と暮らしていた親が親権を得やすく、大抵は母親が一緒に暮らしているケースが多いため、親権獲得率が高くなっているということです。
3.ただし、例外はあります!
・家事育児をおろそかにしていた
・別居時に夫のもとに子供を置いてきてしまった
このような場合は、母親の方に適性があるとは判断されず、母親であろうと親権が取れないことはあります。
親権を得るための方法は?
1.家庭裁判所の判断基準を知ること
裁判で親権を得るための近道は、
裁判所が考える判断基準を押さえ、条件を満たしておくことです。
家庭裁判所が、親権付与者を判断する際に重要視することは…
「子の利益」です。
・子供を十分に養育していけるか?
・子供の成長のためにはどちらを親権者とした方がいいか?
このような点から、親権者を見極められます。
親権とは、親に与えられる「権利」である一方で、
子供の精神的・肉体的な成長を図っていかなければならないという親の「義務」
ということを忘れてはいけません。
2.「子の利益」を考える判断基準

・母性
いわゆる、母親が持つ本能的な愛情。
子供が幼いほど重要視される要素になっています。
ただし、父親であっても、育児を率先してしているなどで母性があると評価される可能性があります。
・現在の監護状況
今現在、子供がどちらの元で育てられているのか。
子供が幼いほど、身の回りの世話(炊事・洗濯・掃除など)をどちらがしているのかが重要視されます。
・住居環境
離婚後、どのような住居に子供と住むのか。
例えば、中高一貫校に通っているのに、転校しなければいけなくなった…など、子供が転校や引越しをしなければならない場合などは考慮されます。
・親権者の健康状態
親権者となる親の健康状態はどうか。
アルコール中毒や精神的不安定などがあれば、親権を得るのに不利になります。
・養育補助者の存在
祖父や祖母など、子育てを手伝ってくれる存在が近くにいるかどうか。
実家の援助などがあり、子供と実際に接する時間が長い方が優先されます。
・経済力
子供を育てていくにあたっての、親としての経済力。
祖父母からの金銭的援助がある場合にはそれも経済力として含まれます。
専業主婦にとっては不安材料の一つだと思いますが、相手方からの養育費の受け取りもあるため、この項目はあまり重要視されないようです。
・離婚原因
離婚原因が子供に悪影響を与えるものでないかどうか。
離婚原因や有責性は、基本的には親権を決めるうえであまり重要視されませんが、不貞行為や暴力などが原因で離婚した場合は、親権に不利に働く可能性があります。
・子供の意思・希望
子供が、母親と父親のどちらのもとにいたいと思っているのか。
子供が小さいうちはこの要素は重視されませんが、15歳以降はとても重要視されます。
・面接交渉の許容性
親権者となる方が、親権者にならなかった方に対して、子供と会うことを許しているかどうか。
正当な理由なく拒絶している場合、親権争いに不利になります。
ただし、子供に対する暴力などがある場合は、例外です。
・兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹がバラバラになってしまわないかどうか。
たとえば、父親は兄だけの親権を希望し、母親は兄弟全員の親権を希望している場合は、母親に有利となります。
子供のために離婚するのかしないのか…
3.子供の年齢との関係
子供の年齢によっては、子供の意思も親権者判断に加味されます。
・0歳~10歳未満
衣食住全般にわたって子供の面倒を見る必要があるため、母親が親権者になるケースが多い。
・10歳以上~15歳未満
子供の精神的・肉体的な発育の状況によっては子供の意思が尊重される。
・15歳以上~20歳未満
子供が自分で判断できるようになるため、子供の意思が尊重される。
・20歳以上
20歳を過ぎれば、そもそも親権者の指定は必要ありません。
年齢が上がるほど、親権者の決定には子供自身の意思がかなり重要となってきます。
だからと言って、親が子供に、どちらの親を選ぶように指示したり強要することは禁じられています。
まとめ
親権獲得が母親に有利なのは、子供にとっては母親の方が必要だと判断されるケースが多いからです。
ですが、決して「母親だから大丈夫」ということではありません。
常日頃から、「子供のために母親としてできること」を考えて行動しておきましょう。
と言うと身構えてしまうかもしれませんが、
子供の食事や身の回りのお世話をこれまで通りしておけば大丈夫(*´з`)
あとは、離婚問題で眉間にしわを寄せたり、子供の前で泣いてしまったりして、余計な心配や不安を持たせないように気をつけてあげましょう。
養育費の取り決めも忘れずに
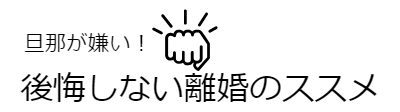














コメントを残す