毎日毎日ケンカばかりして、夫も妻もいつの間にか話をしなくなり、食事も別々、朝も夜も極力顔を合わせないようになった。
だけど、離婚はしないで一緒に住んでいる「家庭内別居」。
はたから見ると、「そんなの夫婦として破綻してるから離婚したらいいのに…」なんて思ってしまうかもしれないけれども、離婚できない事情や離婚しない方が良い事情があるのです。
もし、あなたが「夫とうまくやっていけない」となった時には、どうしますか?
離婚するか、別居するか、家庭内別居するか…?その選択肢は各家庭の事情それぞれなのです。
この記事の目次
家庭内別居をする理由

離婚か別居かを決断する考え方や基準は?注意点と準備すべき事は?
家庭内別居の生活費やルールは?子供への影響は他の家の方法は?
1.自立できるだけの収入がないため
本当は離婚したいけれども、自分に収入がない、または収入が少ないために離婚できない人もいます。
離婚して自力で生活するとなると、家賃や水道光熱費、通信費、駐車場代、保険料、食費などあらゆる費用が必要になります。
仕事から離れて年月が経っている場合は再就職が難しいし、子供がいれば就労時間も限られ、かつ保育料も必要になります。
そのため、就職が決まるまでの間と決めて家庭内別居をしたり、「自分が我慢すれば、とりあえず食べていける」と割り切って家庭内別居を続けている人もいます。
2.離婚の手続きが面倒くさいため
結婚するのは簡単ですが、離婚するのは時間も労力もかかります。
離婚届を提出すれば、確かに離婚成立しますが、子供の親権問題や養育費、財産分与、慰謝料など、決めるべき問題がたくさんあるのです。
特に家を購入してしまっている…などの場合は、考えるだけで億劫になってしまいますよね。
このような手間を考えて、離婚をせずに「ただの同居人」と割り切って淡々と生活する人もいるのです。
3.子供のため
幼い子供がいる家庭の場合、「子供のために今は離婚はしない」と決めている人もいます。
子供の成長や周囲への影響を考えると、「両親がそろっている方がいい」という考えからです。
「今はしない」ということであって、子供が就職したり、成人したら離婚すると期限を決めているところも多いです。
とはいえ、子供も物心がついてくると、両親のギクシャクした様子に気づき、歪んだ家族観を植えつけてしまいそうで、悪い影響が出てしまわないか心配もあります。
子供の教育についても、夫婦が衝突する火種になりやすいものであるため、離婚しないと決めたのであれば、「子供の前では不仲なそぶりを見せない」「教育については2人で話し合う」などの約束も決めておく必要があります。
4.相手方が離婚に応じてくれないため
自分が離婚を望んでいても、相手が望んでおらず、仕方なく一緒に住んでいる人もいます。
離婚するためには、調停で話し合ったり、裁判で争うことになり、時間がかかります。
「もう無理!とりあえず出ていく!」なんて家を飛び出たくもなりますが、夫婦には同居義務があるため勝手に出ていくと「悪意の遺棄」とみなされ、いざ離婚をする際に不利な立場になってしまいます。
何がなんでも離婚したい場合は強硬手段もいいですが、有利な離婚をしたい場合や、離婚はしたくない場合は、一方的に家を出ていく形での別居は避けるべきです。
相手が離婚を受け入れざるを得ないような、決定的な理由を見つけるまでの辛抱です。
5.世間体を守るため
結婚も離婚も、夫婦だけの問題ではなく、家族や親族、職場での立場にも影響が出ます。
そのため、夫婦の意思は「離婚」と固まっているのに、両親や親族から「離婚なんて恥さらしだ」などと世間体を考えて止められている人もいます。
妻は離婚を決意しているのに、夫は職場での立場、信頼、社内評価、昇進など、様々な問題から離婚は避けたいと考えている人もいます。
近年、離婚率が高まっているとはいえ、やはり良い印象は持たれないものです。
離婚せず家庭内別居をするデメリット
1.子供への影響
子供のために離婚はしないと決断した夫婦は多いと思いますが、本当に子供のためになるのでしょうか?
両親が喧嘩ばかりしていたり、口をきいていない様子を見るのは、子供の心に大きなダメージを与えてしまうし、誤った家族像を植えつけてしまいかねません。
中には、ストレスから体調を崩したり、問題行動を起こしたりする子供もいます。
子供にとって本当に良い環境とは、仲が良い両親の間で、何でも話せて、笑って、安心して暮らせる家です。
単に両親がそろっていればいいわけではありません。
離婚しないと決めたのであれば、「子供を傷つけず、不安にさせない」ためにはどうしたらよいかを夫婦でよく話し合いましょう。
2.嫌いな相手と同じ空気を吸うこと
家庭内別居で、食事は別、部屋も別、最低限の関与にしているとはいえ、同居している限り、完全に顔を合わせないことは難しいし、嫌でも話をしなければいけないときがあります。
いくら生活費をもらっているとはいえ、料理をしてあげたり、掃除をしてあげたり、洗濯物を一緒に回すことすら嫌でたまらなくなるかもしれません。
そうなると、家庭内別居ルールを見直して「料理もそれぞれ」「洗濯もそれぞれ」など、より厳しいものにしていくしかないのですが、そうなると生活費をもらいにくくなる気もする…。
「嫌い」な人と一つ屋根の下で暮らすのは、どうしても嫌悪感とストレスがつきまといます。
3.相手が病気やケガをした時の対処
普段は極力顔を合わさずに生活していると思いますが、微妙なのが、相手が病気やケガをした時にどうするのかという点。
相手がインフルエンザになって寝込んでいるとして、普通ならおかゆを作って部屋まで運んであげたり、着替えを手伝ってあげたりなど、ケアをすると思います。
ただ、別居中となればどうするべきなのでしょうか?
どうしようもなく嫌いで家庭内別居をしている状態で、相手がいくら弱っているからと言って手を差し伸べてあげられるのか?
ましてや介護が必要な状態になってしまったら…想像するだけでお先真っ暗な気がします。
4.義父母や親せきとの付き合い
義父母が、家庭内別居状態であることを知っているか、知らないかにもよりますが、いずれにせよ微妙です。
知らない場合は、義父母の前で「普通」を演じなければいけないし、知っている場合は今後どういう付き合い方をするのか決めておいた方が無難です。
子供がいれば、イベントのたびに「どうするか問題」が発生します。
中には、夫は嫌いだが、夫の両親はいい人なので仲良くしているという人もいるようですが、レアケースでしょう。
夫のことが嫌いであれば、そういう人間を育てた親も憎く思えてしまうものだと思いますので。
物理的な距離があれば、会う頻度も少なくていいのですが、近くてかつ不仲である場合は、結構なストレスになる問題です。
5.恋愛・再婚ができない
「ただの同居人」と割り切って生活しているものの、婚姻関係にある以上、恋愛や再婚をすることはできません。
たとえ相手の許可がとれていたとしても、恋愛したことを「不倫」と言われ、離婚を迫られたり、慰謝料を要求されることにならないとは限りません。
6.虚しさを感じる
「一生このまま愛のない偽夫婦を演じるのか?」「もう誰とも愛し合うことなく枯れ果てていくの?」「私の人生なんだったの?」と、虚しさや寂しさを感じることがあるでしょう。
よその楽しそうにしている家族を見るとなおさらです。
割り切って家庭内別居をしていても、ふと虚しさを感じる時はあります。
まとめ

親が離婚していると子供も離婚しやすいって本当?離婚遺伝子って?
1.家庭内別居を選択する理由は、各家庭それぞれにあるが、大部分を占めるのは、「金銭面」と「子供への影響」と言える。
2.メリットを感じて家庭内別居を選択したものの、やはりデメリットはつきもの。
デメリットが嫌ならば、離婚を視野に入れるか、デメリットを解消できるような手立てを考えるしかない。
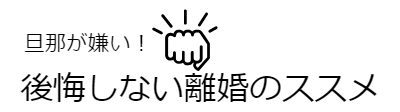














コメントを残す