「死後離婚」って聞いたことありますか?
夫の死後に、夫の親族と縁を切ったり、籍を抜いたりすることなんですが、増えているそうなんです。
夫を許せない、残された舅や姑の世話なんて無理、同じ墓に入りたくない…など、様々な思いが伺えます。
ただ、離婚するとなると、遺族年金や遺産相続の権利についてはどうなるのか疑問ではないですか?
そもそも、夫が死んだ後の姑の扶養義務はあるのでしょうか?
この記事の目次
死後離婚とは

1.夫が死んだ後「離婚届」を提出?
「ずっと離婚したくてたまらなかったけどできなかった」
「死んでくれてやっと自由になれた」
こんな思いを抱えて生きてきた人は、夫が亡くなった今からでも離婚したい気持ちが強いかもしれません。
とはいえ、夫が亡くなった後でも離婚することはできるのでしょうか?
実は、「死んだ夫と離婚する」というような制度はないし、必要もありません。
なぜなら、配偶者が死亡すると婚姻関係も終了するため、離婚届を提出するようなことをしなくても、離婚したのと同じような状態になるからです。
そのため再婚をすることもできます。
2.通常の離婚と違う点
通常の離婚と異なるポイントは2点あります。
●夫の親族との関係は継続する
通常の離婚であれば、離婚と同時に夫や夫の親族との関係が断たれますよね。
ですが、夫が亡くなった場合は、夫との婚姻関係は終了するものの、夫の親族との関係は変わらず続くのです。
結婚当初から姑にイビられていた妻などは、夫の死後も姑との関係が続くなんてとてもじゃないですよね。
でも大丈夫です。手はあります。
そういう方は、「姻族関係終了届」を役場に提出すれば、夫の親族との関係を断つことができます!
★姻族関係終了届の提出についてはこちら
⇒ 姻族関係終了届の入手提出先と書き方は?絶縁状で姑に仕返しする妻急増
●苗字はそのまま変わらない
通常の離婚であれば、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻時の苗字を名乗り続けるか選択できます。
一方、夫が亡くなった場合は、苗字をどうするか選択する場はとくに与えられません。
とはいえ、旧姓に戻すことはできます。
もし、「夫の苗字から解放されたい」という場合は、「復氏届」を市町村役場に出せば、結婚前の名字に戻すことができるし、戸籍も別にすることができます!
注意点としては、子供の苗字は「復氏届」を出しても変更されません。
子供の苗字も変更するには別の手続きが必要になります。
まず、「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出し、子供の苗字を変える許可が出たのちに、「入籍届」を市区町村役場に提出することが必要となります。
ちなみに、妻(母親)が「姻族関係終了届」を提出しても、子供と夫の親族との関係は断つことができないため、こちらも注意が必要です。
姻族関係終了届で遺族年金や遺産相続も終了?
1.遺族年金はどうなる?
答えは、「もらえます」。
「姻族関係終了届」を提出して夫の親族との縁を切っても、「復氏届」を提出して旧姓に戻しても、「新戸籍」を作って夫の戸籍から抜けても、遺族年金をもらい続けることができるのです。
というのも、遺族年金をもらう権利を失うのは、以下に該当した場合との定めがあるからです。
・死亡したとき
・婚姻したとき
・直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき
・離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき(離縁=養子縁組解消のこと)
・30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
2.遺産相続はどうなる?
答えは、「もらえます」。
遺産相続の権利は、配偶者が亡くなった時点の関係性(相続対象人であるか)で判断されるため、夫の死後にどうしようとも遺産相続を受けることができます。
なお、夫の死後に舅や姑が亡くなった場合は、子供(姑にとっての孫)にその遺産相続の権利がいきます。
死後離婚増加の原因は姑の介護や墓問題?

1.夫の死後も姑の扶養義務はあるの?
夫と姑と3人で暮らしていたけれども、夫が亡くなり、姑との2人暮らしになってしまった。
どんなに姑が良い人であったとしても、今後の生活や関係性に不安や疑問を感じてしまう人は多いのではないでしょうか。
関係が悪ければ、すぐにでも縁を切るべく「姻族関係終了届」の出番です。
とはいえ、そもそも夫が亡くなった後、夫の親族を扶養する義務はあるのでしょうか?
民法877条では、生活のために経済的な援助を必要としている人を扶養する義務を負うのは、原則として直系血族および兄弟姉妹とされています。
ただし、特別の事情がある時は、3親等内の親族が扶養義務を負うこともあるともされています。
ということは、姑と嫁の関係は直系血族ではないし兄弟姉妹でもないため、「嫁が姑を扶養する義務はない」ということになります。
ただ、もし姑に直系血族がいなかったり、兄弟姉妹がいないなどの特別な事情がある場合には、家庭裁判所から姑の扶養を命じられる場合があります。
こうなると、やはり「姻族関係終了届」の出番で、これを提出することで扶養義務から逃れることができます。
2.同じ墓に入らなければいけないもの?
夫婦だから、親族だからといって、同じ墓に入らなければならないということはありません。
もちろん、そんな法律もありません。
ですから本当は、同じ墓に入りたくないという理由で「姻族関係終了届」を提出する必要はないのです。
とはいえ、夫の親族に「なぜ嫁に来たのに〇〇家の墓に入ってくれないの?」「〇〇家のお墓を守り続けてね」など言われると、断りにくいものがありますよね…。
そんな時は「姻族関係終了届」で夫の親族との関係を断つことが手っ取り早いと思われます。
ただ、姑と同じ墓に入りたくないけれど、夫の墓参りはしたい…なんていう場合は注意が必要です。
絶縁状を突きつけられた姑が、「縁を切ったのなら墓にも近づかないで!」と怒ってしまう可能性がありますので…。
まとめ

いかがでしたか?
死後離婚は、夫の親族と縁を切ることができるうえに、遺族年金ももらえるし、遺産相続も受けることができるなど、メリットがたくさんです。
逆に、デメリットと言えば、お墓を自分で準備する必要があること…くらいでしょうか。
美味しいとこどりともいえる死後離婚ですが、期限はありませんので、じっくり考えてベストな選択をしていただければと思います。
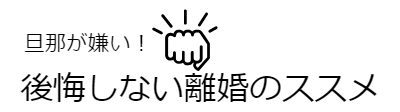














コメントを残す