面会交流を拒否することはできるのでしょうか?
さんざんな目にあって離婚した場合などは、このまま縁を切りたいものですよね…。
そんな方に朗報!?
面会交流は事情によっては拒否や制限をすることができます。
早速、その条件や方法についてみていきましょう。
この記事の目次
面会交流を拒否したり制限することはできる?
面会交流を拒否することができる条件は?
面会交流を行うことが子供の利益や福祉に反する場合は、拒否や制限することができます。
それ以外の場合は面会交流を行う必要があります。
子供の利益や福祉とは?

子供の利益や福祉というと、何を示すのかいまいちピンときにくいもの…。
「子供の成長にプラスになるか?」と考えると分かりやすいかもしれませんね。
つまり、面会交流は、子供の成長にプラスとなるような方法や内容で行われる必要があります。
面会交流が子供の利益や福祉に反するとされる事例
逆に、子供の成長にマイナスになるような行為があれば、面会交流の拒否や制限を検討するべき事象となります。
たとえば、子供に精神的な不安や動揺を与えるような行為をした場合。
・子供を連れ去ろうとした
・勝手に子供と会った
・子供や同居している母親に暴力をふるった
その他こんな場合も、制限理由として認められる可能性があります。
・子供が会うことを拒否している
・相手が養育費を支払わない
・面会時に相手から復縁を迫られた
・面会時に相手から金銭を無心された
・再婚して新しい父親との生活が営まれている
特に思春期の子供は敏感なため、別居している親と会うことで精神的な動揺を与えてしまうことがあります。
このような場合は、一時的に面会を制限したり、方法を見直すなど、子供への影響を考えた臨機応変な対応が求められます。
面会交流拒否や制限をする方法は?
相手(父親)と話し合う
面会交流相手(父親)と話し合いましょう。
一方的に拒否したり取りやめてしまうと、後で慰謝料や損害賠償などの請求をされかねません。
●まずは、継続する方法を模索すること
話し合いを持つ際は、できる限り面会交流を継続することを目指して行いましょう。
問題点を解決できるように、面会方法や条件等の見直しをするのが有効です。
たとえば、子供が「会いたくない」と拒否している場合、思春期を抜けるまでの間について面会を中止したり、同居している母親や第三者同伴の元で会うなどの方法も考えられます。
●どうしても継続できない場合は…
面会交流を継続できない事情や理由を説明しましょう。
ただし、相手から継続するための条件を提案された場合は、前向きに検討してみることが大切です。
●相手によっては拒否⇒制限で交渉を
制限をかけたいけれど、相手が受け入れてくれなさそう…という場合は、まず面会交流拒否の話をするのも手です。
相手が抵抗してきたところで、「百歩譲って〇〇してくれるのなら…」と譲歩する姿勢を見せつつ条件を提示すると、相手も受け入れてくれやすいかもしれませんね。
話し合いで決まらない場合は調停を
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てましょう。
調停では調停委員を介して話し合いが行われ、それでも不成立となった場合は、審判で決められることとなります。
ちなみに、離婚調停時に面会交流をするよう条件面を決めてしまった…という場合でも、子供への悪影響が認められれば制限や中止される場合があります。
面会交流を気持ち良くするために
さいごに
面会交流をすることが子供の健全な成長を阻害するものである場合は、拒否や制限をするべきです。
ただし、安易に拒否や制限をするのではなく、まずは継続できる方法を模索することが大切です。
とはいえ、これが難しいんですけどね…(;´・ω・)
話し合いが難しいようであれば、家庭裁判所の調停を利用し、くれぐれも「無視」や「一方的に」といった態度はとらないように気をつけましょう。
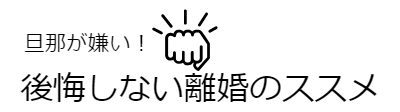

















コメントを残す